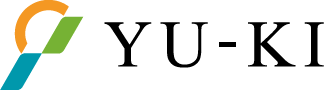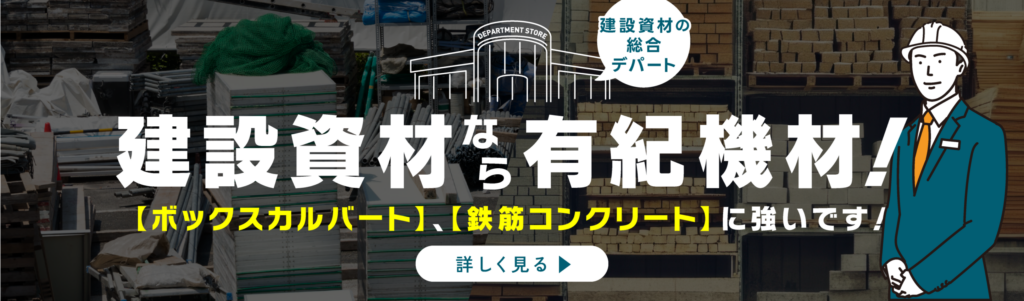解体工事や新築工事で発生するコンクリートや木材などの建設資材をどう処理するかは、建築業界にとって大きな課題です。現場では次のような悩みがよく聞かれます。
- どの工事や資材が「建設リサイクル法」の対象になるのか分からない
- 届出や分別解体の義務が複雑で、正しく対応できているか不安
- 廃棄物処理コストを抑えつつ環境に配慮した施工を行いたい
こうした課題に対応するのが**「建設リサイクル法」**です。本記事では法律の仕組みと対象工事、再資源化の流れを整理し、現場での活用方法を解説します。理解を深めることで、法令遵守だけでなく、コスト削減と環境配慮を両立する施工管理につなげることができます。

有限会社 有紀機材
代表 赤井 勇貴
本記事をご覧いただき、ありがとうございます。
15年の現場経験と、1級土木施工管理技士・測量士・技術士補の国家資格に基づき、建設資材の品質とコストに直結する「心から信頼できる実用的な知識」を、現場目線でお届けいたします。 皆様の確実な業務遂行の一助となれば幸いです。
建設資材のリサイクル「建設リサイクル法」とは?
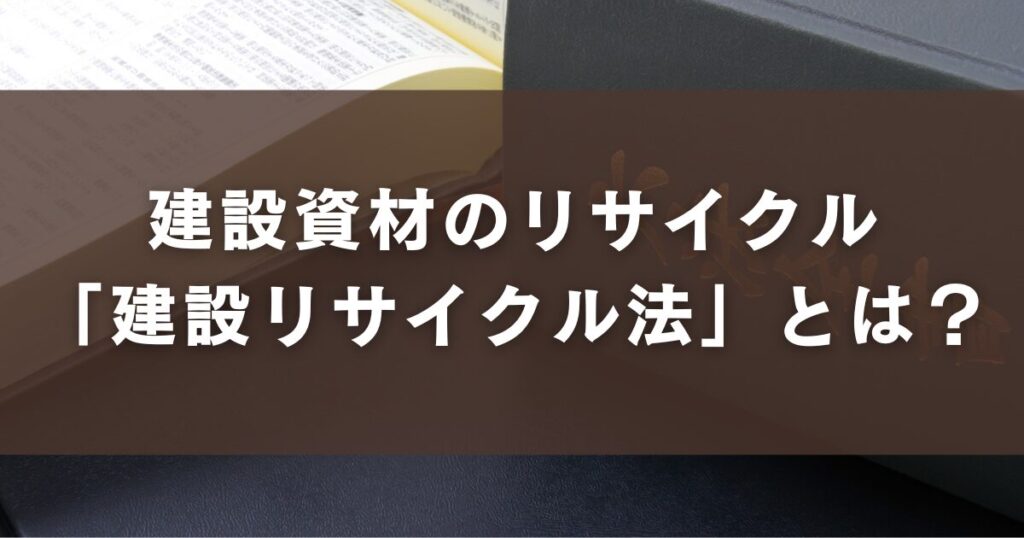
建設リサイクル法は、正式名称を「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」といい、2000年5月に制定されました。解体や新築などの工事で発生する建設廃棄物を適切に分別・再資源化し、環境負荷を軽減することを目的としています(参照:環境省「建設リサイクル法の概要」)。
制定の背景と目的
- 建設工事は国内の産業廃棄物の約2〜3割を占めると言われ、処理方法が社会問題となっていた
- 最終処分場の不足や違法投棄の増加を防ぐため、法的枠組みでの管理が必要になった
- 資材を分別解体し再利用することで、循環型社会を推進することが最大の目的
この背景から、特にコンクリート塊や木材など再資源化しやすい資材が対象として定められました。
対象となる工事や資材の種類
法律では、一定規模以上の建築物や土木工事が対象となります。
- 解体工事:延べ床面積80㎡以上の建築物
- 新築工事:延べ床面積500㎡以上の建築物
- 土木工事:請負金額が500万円以上の場合
対象資材は以下のようなものです(参照:国土交通省「建設リサイクル法の対象となる建設工事」)。
- コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊
- 木材
- 建設発生土や建設汚泥
- 廃プラスチック類
法律上、これらの資材は分別解体と再資源化が義務付けられており、違反した場合は罰則の対象となります。

建設リサイクル法に基づく手続きと義務
建設リサイクル法では、対象となる工事を発注する側・施工する側に対して、明確な手続きと義務が定められています。適切に対応しなければ罰則の対象となるため、事前に内容を把握しておくことが重要です。
届出が必要となる工事規模
一定規模以上の工事では、着工前に都道府県知事への届出が義務付けられています(参照:国土交通省「建設リサイクル法の対象となる建設工事」)。
- 解体工事:延べ床面積80㎡以上
- 新築・増築工事:延べ床面積500㎡以上
- 修繕・模様替工事:請負金額1億円以上
- 土木工事:請負金額500万円以上
届出を怠った場合は罰則や指導の対象となり、現場がストップするリスクもあります。
発注者・施工業者に求められる責任
法律の義務は施工業者だけでなく、発注者にも及びます。
- 発注者は、契約時に分別解体や再資源化に対応できる業者を選定する責任がある
- 施工業者は、現場での分別解体の実施、再資源化施設への適正な搬入を行う義務がある
- 廃棄物処理法と連動しているため、マニフェスト管理も求められる
「発注者と施工業者が双方で責任を分担する」という点が特徴であり、業界全体でのコンプライアンスが求められています。

再資源化の対象となる建設資材
建設リサイクル法では、再資源化の対象となる資材が具体的に定められています。これは、再利用やリサイクルの実績が高く、環境負荷低減に直結するものが中心です(参照:環境省「建設リサイクル法の概要」)。
コンクリート塊やアスファルト
- 解体工事で大量に発生する代表的な資材
- 再生砕石や道路舗装材として利用される
- リサイクル率が非常に高く、資源循環に大きく貢献

木材や建設発生土
- 木材はチップ化してボード材や燃料に再利用される
- 建設発生土は盛土や埋め戻し材として再活用が可能
- 現場ごとに性質を見極め、適正に分別することが重要
廃プラスチックや建設汚泥
- 廃プラスチックは再生樹脂や固形燃料に転換される
- 建設汚泥はセメント原料や土質改良材として再資源化される
- これらは処理コストがかかるため、効率的な処理ルート確保が鍵
これらの資材を現場で適切に分別・処理することで、廃棄物量を削減し、循環型社会の実現に近づきます。
現場での分別解体と運用ポイント
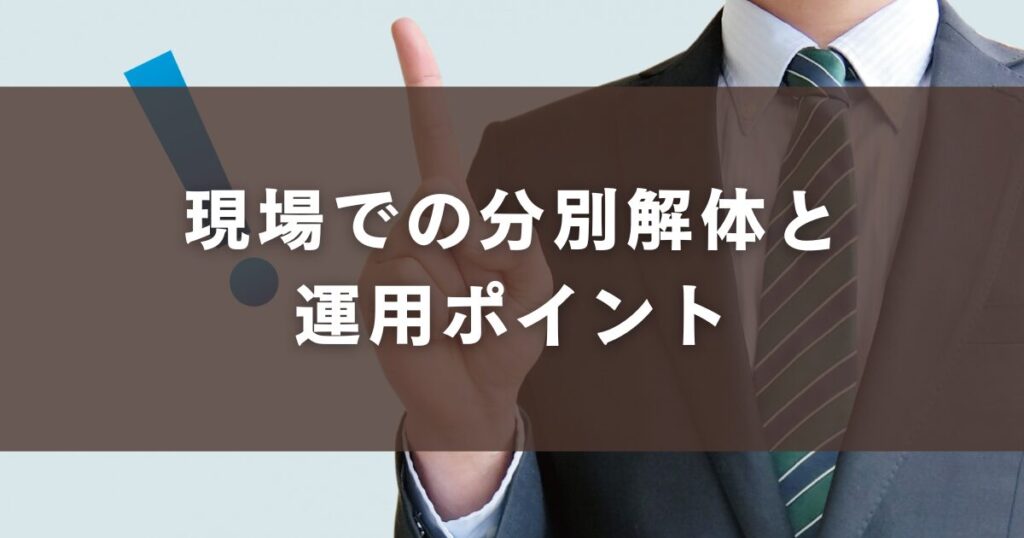
建設リサイクル法の実効性を高めるには、建築現場での分別解体を適切に行うことが不可欠です。現場での運用方法を理解し、効率的に廃棄物を再資源化につなげることが求められます。
解体工事での分別の流れ
- 解体計画の段階で、対象資材(コンクリート・木材・アスファルト等)を確認
- 現場で混合しないように分別しながら解体を進める
- 資材ごとに処理業者やリサイクル施設へ搬出
現場での分別が適切に行われるかどうかが、再資源化率を大きく左右します。
新築工事での副産物処理
- 新築工事でも木材端材、建設発生土、廃プラスチックなどが発生
- 工事工程ごとに分別ルートを設け、廃棄物混合を防ぐ
- 副産物の再利用先を確保することで、処分コスト削減と環境配慮を両立
こうした仕組みを設計段階から取り入れることで、現場全体での廃棄物排出量を減らす取り組みが実現できます。
建設リサイクル法がもたらす効果と課題
建設リサイクル法は、建設業界における廃棄物の扱い方を大きく変えました。環境負荷の軽減や資源循環の推進につながる一方で、現場での課題も少なくありません。
環境負荷の軽減と循環型社会の推進
- 再資源化率が向上し、最終処分量が減少
- 違法投棄や不適正処理が減り、地域環境の保全に寄与
- 資材を「廃棄物」ではなく「資源」として循環利用できる仕組みが整った(参照:環境省「循環型社会形成推進基本法」)
コスト削減と資材再利用の可能性
- 再利用できる資材は新規購入を抑えられ、コスト削減につながる
- 再生砕石やリサイクル木材など、新しい建設製品として市場に還元
- 循環利用による建設副産物の有効活用が経済的なメリットも生んでいる
現場で直面する課題
- 解体現場での分別作業に手間と時間がかかる
- 再資源化施設が地域によって不足しており、搬送コストが増加
- 現場ごとの運用レベルに差があり、制度の実効性にばらつきがある
こうした課題を解決するためには、発注者・施工者・行政が連携して仕組みを強化することが求められています。
まとめ|建設リサイクル法を理解して現場で活用する
建設リサイクル法は、解体工事や新築工事で発生する建設資材を分別し、再資源化することを義務付けた法律です。コンクリート塊や木材、アスファルトといった主要資材は再利用ルートが確立されており、適切に対応することで廃棄物を大幅に減らすことができます。
現場での分別解体を徹底すれば、環境への負荷を抑えるだけでなく、再生資材を有効活用することでコスト削減にもつながります。逆に、分別や届出を怠ると罰則の対象となり、工事そのものが停止するリスクもあるため注意が必要です。
法律を正しく理解し、現場で運用できる体制を整えることが、持続可能な建設業を実現する第一歩です。 発注者と施工者が協力し、行政やリサイクル施設と連携することで、環境配慮と経済性を両立した建築活動が可能になります。
信頼できる建設資材の調達先をお探しなら、有紀機材にお任せください。
35年以上の実績と、資材販売から施工提案まで対応するワンストップ体制で、現場の課題に的確にお応えします。対応エリアでの安定供給と現場支援に強みを持つ当社にぜひご相談ください。